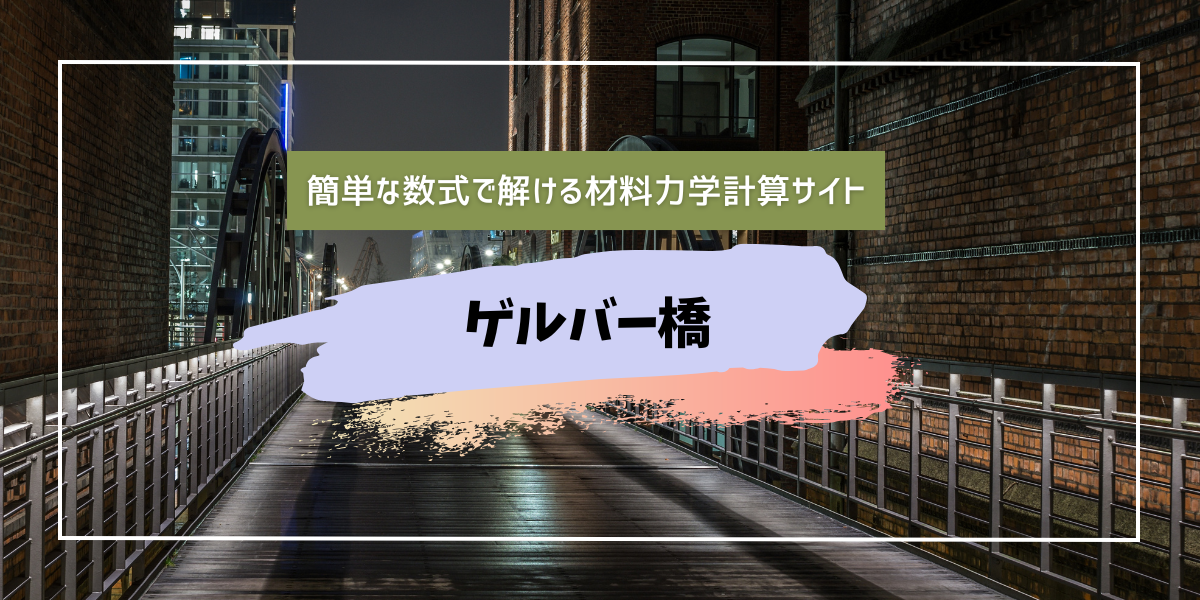今回は、「ゲルバー橋」についてお話ししていこうと思います。
ゲルバー橋は、途中にヒンジ(可動部分)を設けることで、スパンが長くなっても強度をしっかり保ちながら、施工までラクにしちゃうという、とても便利な構造なんです。
「あんまり馴染みのない名前だな…」と思う方も多いかもしれません。実際、テレビや雑誌などで頻繁に特集されるわけでもないので、聞いたことがないのも当然かもしれませんね。
そこでこの記事では、ゲルバー橋とはどんな橋なのか、どんな特徴やメリットがあるのか、そしてなぜそんな構造になっているのかを、なるべくわかりやすく解説していきたいと思います。
それではさっそく、ゲルバー橋の世界をのぞいてみましょう!
ゲルバー橋とは

ゲルバー橋は、橋を支えるはりの途中に「ヒンジ」と呼ばれる可動部分を入れて、いくつかの「単純支持はり」をつないでいる橋のことです。このヒンジがあるおかげで、橋がたわむとき力が分散されて、全体的にムリなく荷重を支えられる仕組みとなっています。
一般的な単純支持はり(単純桁)だと、それぞれはりの両端に支点があって構造は単純ですが、支間が長くなると強度を確保するのが難しくなってきます。一方、連続はり(連続桁)では支点が等間隔でつながっていて強度的に有利ですが、その分設計や施工が大変になり、現地での施工作業と部品コストも上がってしまいます。
このような場合、ゲルバー橋という単純支持はり(単純桁)と連続はり(連続桁)の「いいとこ取り」を使ってこの課題を解消できるんです。
ゲルバー橋は、はり(もしくは橋)の途中にヒンジを入れて荷重をうまく分散し、単純桁と連続桁のメリットを両立させた構造のことをいいます。
このヒンジを入れることで、施工のしやすさ、荷重分散のメリット、コスト面でのメリットがあります。
ただ、このヒンジの部分は可動部分(回転して動くところ)なのでそこがほかの部材より摩耗しやすくなってしまいます。ですから定期的な点検やメンテナンスが発生する、というのもポイントです。
ゲルバー橋の概要・歴史的背景

ゲルバー橋っていう呼び名は、実はドイツの技術者ハインリッヒ・ゲルバー(Heinrich Gerber)さんの名前から来てるんです。19世紀後半頃に、橋の途中にヒンジを入れるっていう今のゲルバー橋の原型を考案した人で、当時の鉄道橋とかに採用されて一躍注目を集めたすごい人なんだ。
当時の橋づくりは、長いスパンをどうやって支えるかがしばしば問題になっていました。単純桁で大スパンをカバーしようとするとめちゃくちゃ頑丈な部材が必要だったし、かといって全部を連続桁にすると技術的にも費用的にもハードルが高かったんです。そこで部分的に分割してそこで荷重を分散してしまえ!という発想でヒンジを入れることを考えたのがこのゲルバー先生(仮に呼んでます)なんです。
その後、このアイデアは世界各地に広がって鉄橋が盛んに作られた時代に、コストや施工性をある程度抑えながら頑丈な橋を作る手段として重宝されたんです。もちろん時代が進むにつれて材料の性能も上がったり、コンピュータ解析による複雑なシュミレーションのおかげで、より強度(剛性)を持った橋を造ることができるようにもなったけど、ゲルバー橋のアイデア自体は「いまも十分に使える有効な方法」として残ってるわけなのです。
簡単に言うと、ゲルバー橋は歴史の中で「当時の技術や材料の制限をうまく乗り越えるためのアイデア」から生まれて、それが現代にも受け継がれている構造形式ってわけだね。
材力学的観点からのメリット

ゲルバー橋がいいところを力学的な観点から見ていきましょう。
ゲルバー橋のどこがいいの?って話ですが、簡単に言うと「ムリなく荷重を分散できる」というのが一番大きなポイントです。
応力分布の特徴
橋の桁には、車両の重さや自重(橋自体の重さ)などがかかりますが、それが曲げモーメントやせん断力などに変化して荷重が分布します。ゲルバー橋の場合、中間ヒンジがあることで以下のような違いが生まれます。
- ヒンジがある部分でモーメントが切れるということ
連続桁では1本の桁が繋がっているため、支点だけでなく、その間の部分(支間中央付近)に大きな曲げモーメントが発生することが多いです。
一方、ゲルバー桁はヒンジを境にしてそれぞれ「独立した構造」となるので、モーメント荷重がここで分割され、全体に大きな応力がかかりにくくなります。 - ヒンジの部分では応力集中が起こりにくいということ
「ヒンジがあるとそこに応力が集中しそう…」と思うかもしれませんが、実際には「回転が許される」構造なので、逆に桁全体の曲げモーメントを分散できます。ただし、せん断力や軸方向力などはヒンジ部分を通過するので、別の形で局所的な力が生まれる場合もあり、そのあたりは設計や補強で対処します。
荷重を計算するときポイント

ゲルバー橋を計算する際のポイントは、以下の内容を押さえておくとイメージがしやすいです。
- 支点反力を部分的に計算できるということ
完全な連続桁だと、各支点がどれだけ反力を受け持つかが一体の構造計算になるため、数式がややこしくなりがちです。一方、ゲルバー橋だとヒンジを境界にして考えられる部分が出てくるので、「この支間分は単純支持はりに置き換えて計算」、「となりの支点は別として計算」と、分割して計算できるのでとても便利です。 - ヒンジにより一部の反力が制御される
ヒンジがあることで、曲げモーメントの伝達が制限され、反力の流れもある程度コントロールしやすくなります。
とはいえ、ヒンジ周辺でどう力が伝わるかはちゃんと考慮する必要があるので、設計段階では力の流れをしっかり可視化して考えることが重要になります。 - 段階的な施工を考慮しておくことも必要
橋は現場で一気に完成形になるわけではなく、部分的に架設したり、コンクリートを順番に打設することも多いです。その工程ごとで力のかかり方が変わってくるので、「施工段階ではこの支点に重量が集中」「完成後はヒンジを通して別の分配になる」など、施工の要所要所でどのように荷重が発生するのかを考えた計算が必要となります。
中間ヒンジ部分でのモーメント分布について

ゲルバー橋のキモとも言える中間ヒンジは、橋の長いスパンをいくつかの単純スパンに分ける働きをしています。モーメント(曲げ荷重)がどう分配されるかについては、ざっくり言うとこんな感じです。
- 回転を許容してモーメントが伝わりすぎないようにする
もしヒンジなしで桁が連続していると、例えば片側のスパンに大きな荷重が発生した際、両側の支間に影響が及びます。しかしヒンジがあると、回転が自由なので、過度にモーメントが隣のスパンへ移動しないという特徴が生まれます。 - 荷重を受けたときのたわみの制御
ヒンジを挟んだ各スパンが独立して回転できるため、単純桁(単純支持はり)に近い挙動になります。これにより、必要以上に曲げモーメントが部材に溜まらず、たわみ量も比較的コントロールしやすくなります。 - 適切なヒンジ位置の選定が重要
ヒンジをどこに設置するかで、モーメントの分配は大きく変わります。たとえば、
スパン中央に置けば、左右対称でシンプルになる。
少し中央からずらして、施工条件や下部構造の配置に合わせる。
と、周辺の環境なども考慮しながら、どこにヒンジを設ければいいのかが重要になります。
どのような場面で採用されるのか(設計上の特徴と利点)

ゲルバー橋は、橋のスパン(支店と支点の間)がそこそこ長いけど、全部連続にするほど大掛かりにはしたくはないしコストも抑えたい…みたいなシチュエーションにぴったりだということは先ほどお伝えしましたね。
じゃあ、どういったところでこのゲルバー橋が使われているの?と疑問に思う方もいるかもしれません。
次は、そこについてお話しますね。
ゲルバー橋がどういったところで使われるのかは主に以下のようなシチュエーションで用いられてます。
- 中規模の川や谷をいくつかまたぐ時
1本ずつ単純桁にすると部材が増えすぎるし、連続桁にすると工事が複雑になりがち……そんなとき、ゲルバー橋ならちょうどいいコストと施工のしやすさが期待できます。 - スパンがそこそこ長めで、補強や維持管理を見据えたい時
連続桁は一体化しているぶんメンテナンスの手間や方法が限られることもあります。しかし、ゲルバー橋ならヒンジ部分である程度区切りがあるから、部分的な補修がしやすいくなるメリットがあります。 - 施工を分割して進めたいプロジェクトに向いている
単純桁感覚で部材の運搬や架設ができるところもメリットです。なので、工期や人員を臨機応変に調整しやすいのもポイントです。
単純桁だけだと強度やスパンの制限が気になるし、全部連続桁にしてしまうと設計・施工がややこしくなってしまう・・・そんな悩みを解消してくれるのが、このゲルバー橋なんです。
世界三大ゲルバー橋って?

このようにいろいろなメリットがあるゲルバー橋ですが、世界的に(知る人ぞ知る)有名な「世界三大ゲルバー橋」と呼ばれる有名な橋が存在するんです。
日本の橋もあるので、簡単にそれぞれ紹介したいと思います!
ケベック橋
カナダのケベック市近くで、セント・ローレンス川をまたいでいる大きな橋がこのケベック橋です。3径間のカンチレバー形式トラス橋で、中央径間が549mもあるのが特徴です。
実は1907年と1916年の建設中に2度の大事故が起きていて、完成したのは1917年です。このことから、悲劇の橋とも言われているけど、その経験を教訓に多くの技術的な進歩がここから生まれ、いまでは鉄道や自動車が通行できる、ケベック州のシンボル的存在になっています。
フォース鉄道橋
フォース鉄道橋は、スコットランドのエジンバラ近くのフォース湾を横断する大きな鉄道橋です。実は2つの橋が並んでいて、昔からある鉄道橋を指して“フォース鉄道橋”って言うようになりました。ちなみにもう1つの吊橋はフォース道路橋といいます。
この鉄道橋は最大支間が約520mという大スケールなのに、1889年に完成した歴史のある橋です。19世紀に造ったってすごいよね。しかも当時は鋼材を革新的に使ったり、主要圧縮部材をパイプ形状にするなど、画期的なアイデアが盛り込まれていたらしいです。
港大橋
大阪市の港区と南港地区をつなぐ、真っ赤な鋼道路橋です。橋長980mで、その中央径間はなんと510mある。カンチレバートラス構造としては世界第3位の長さを誇っています。
港大橋は1974年に完成していて、上階は阪神高速道路湾岸線、下階は一般道路という2層構造になっています。ここまでの規模だと負荷荷重が大きくなるから、当時としては珍しかった70kgf/㎟や80kgf/㎟級の高張力鋼を使ってて、極厚板材を特注で作ったんだって。ちなみに大阪の街並みと風景も楽しめる橋だから、夜景スポットとしても人気のある場所です。
この3つは、カンチレバー形式のトラス橋としてよく「世界三大ゲルバー橋」として紹介されるているんですが、実は厳密に言うと「ゲルバー橋」と「カンチレバー橋」は少し違うところがあります。
でも、構造的に似ている部分が多いので、この2つをまとめて語られることが多いんです。
まとめ
ゲルバー橋は、単純桁と連続桁、それぞれのメリットを組み合わせた橋梁形式です。
途中にヒンジを入れることで荷重を分散しやすくなり、施工やメンテナンスの自由度も高められます。一方で、ヒンジ部分の摩耗や補修は欠かせず、連続桁ほどシームレスでもありません。そんな“いいとこ取り”な構造のおかげで、中規模から大規模の橋に柔軟に対応できるのがゲルバー橋の強みといえるでしょう。
橋づくりにはさまざまな工夫や技術が詰まっていますが、その中でもゲルバー橋は一歩先を行くアイデアが現在でも活きている、魅力ある構造形式です。